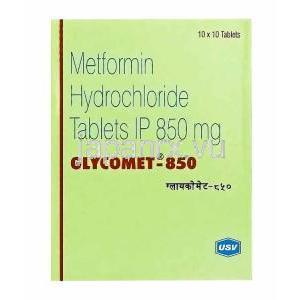【クロルプロパミド】食事と一緒に服用下さい。
【クロルプロパミド】紅潮、心拍数の増加、吐き気、喉の渇き、胸の痛み、アルコールによる低血圧(ジスルフィラム反応)などの症状を引き起こすことがあります。
【クロルプロパミド】クロルプロパミドは、妊娠中に使用するのは危険である可能性があります。 動物研究は胎児に悪影響を及ぼしていますが、ヒトの研究では限られています。医師にご相談ください。
【クロルプロパミド】母乳育児中の使用は危険です。研究データでは、この薬剤が乳児に毒性を引き起こすか、または母親の母乳栄養が望ましくない状態となることが示唆されています。 治療中は乳児の血糖を監視する必要があります。
【クロルプロパミド】通常、車の運転などに影響を及ぼすことはありません。
【クロルプロパミド】腎疾患がある場合は、注意が必要です。用量調整の必要がある可能性があります。医師へご相談下さい。腎疾患が重度である場合は、推奨されません。
【クロルプロパミド】肝疾患がある場合は、注意が必要です。用量調整が必要となることがあります。医師へご相談下さい。
シルデナフィル
- 滅多に起こらない相互作用 もしくは相互作用なし
イトラコナゾール - 一般的な相互作用
イトラコナゾール ブデソニド - 一般的な相互作用
イトラコナゾール ブデソニド プレドニゾロン - 深刻な相互作用
イトラコナゾール ブデソニド プレドニゾロン パンクレアチン - 深刻な相互作用
イトラコナゾール ブデソニド プレドニゾロン パンクレアチン プロプラノロール - 深刻な相互作用
イトラコナゾール ブデソニド プレドニゾロン パンクレアチン プロプラノロール パロキセチン - 深刻な相互作用
イトラコナゾール ブデソニド プレドニゾロン パンクレアチン プロプラノロール パロキセチン セルトラリン - 深刻な相互作用
イトラコナゾール ブデソニド プレドニゾロン パンクレアチン プロプラノロール パロキセチン セルトラリン ラベタロール
クロルプロパミド (アベマイド ジェネリック)

クロルプロパミド (アベマイド ジェネリック)の使用方法
クロルプロパミド (アベマイド ジェネリック)は、2型糖尿病の血糖コントロールを改善するために使用される経口血糖降下薬です。食事療法や運動療法と併用して用いられます。キャンディやブドウ糖など、すぐに糖分を補えるものを常に携帯することが推奨されています。低血糖症状(発汗、冷や汗、動悸、混乱など)が出た際に、すぐに糖分を摂取することで悪化を防ぐことができます。
クロルプロパミド (アベマイド ジェネリック)の効能・効果
膵臓のβ細胞を刺激し、インスリンの分泌量を増やすことで、血糖値を下げる作用があります。
効果の持続時間が長く、強力な血糖降下作用を発揮することが特徴です。1型糖尿病には使用できません。
クロルプロパミド (アベマイド ジェネリック)の一般的な副作用
主な副作用には、低血糖(動悸、発汗、冷感など)、吐き気、頭痛、めまいなどが報告されています。
副作用が長期間続く場合や、症状が重い場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
よくある質問
クロルプロパミドは、スルホニル尿素系に分類される2型糖尿病治療薬で、膵臓からのインスリン分泌を促すことで、血糖値を下げる働きを持ちます。通常は、食事療法や運動療法と併用して用いられます。
Q. クロルプロパミド (アベマイド ジェネリック)の作用機序は?
クロルプロパミドは、スルホニル尿素受容体(SUR)に結合することで、膵β細胞膜のカリウムチャネルを閉じ、細胞内のカルシウムを増加させます。これによりインスリンが分泌され、血糖値を低下させる作用を発揮します。
Q. クロルプロパミド (アベマイド ジェネリック)の強さは?
同系統の薬剤の中でも作用が強く、持続時間も長いのが特徴です。個人差があり、低血糖のリスクもあるため、必ず医師の指示に従って使用してください。
Q. 2型糖尿病とは何ですか?
インスリンの分泌低下やインスリン感受性の低下により、血糖値が高くなる病気です。生活習慣や遺伝が関係し、初期は自覚症状が少ないこともあります。
【参照文献】一般社団法人 日本内分泌学会
Q. クロルプロパミド (アベマイド ジェネリック)の口コミは?
「血糖値が安定した」「1日1回の服用で済むので便利」という声が多い一方、「低血糖に注意が必要」との意見もあります。
基本情報
2型糖尿病は、生活習慣や遺伝的要因が深く関与しており、適切な治療を行わないと、失明や腎不全による人工透析など重篤な合併症を引き起こす恐れがあります。特に、初期には自覚症状がほとんどなく、気づかないまま進行することもあります。
クロルプロパミド(アベマイド ジェネリック)は、膵臓のランゲルハンス島にあるβ細胞に作用し、インスリンの分泌を促進することで、血糖コントロールの改善に効果を発揮します。

【参照文献】KEYENCE
用法・用量
*添付文書をよく読み、医師に指示された服用方法に従ってください。
*用量は病状等により異なりますので以下は目安としてお読みください。
通常、1日100〜250mgを朝食前または朝食時に1回経口投与します。
効果や副作用により医師の判断で最大1日500mgまで増減される場合があります。
高齢者や低体重の方には、50mgから開始されることもあります。
警告
・重度で遷延性の低血糖を起こす可能性があるため、用法・用量は必ず医師の指示に従い厳守してください
・高齢者や栄養状態が不良な方、激しい運動を行う方では低血糖のリスクが高まります
・アルコールは低血糖を重症化させる恐れがあるため、飲酒は控えてください

禁忌
以下に該当する場合は使用できません。
・1型糖尿病(インスリン依存型糖尿病)
・糖尿病性ケトーシス、昏睡または前昏睡
・重篤な肝機能障害または腎機能障害
・重度の胃腸障害(下痢、嘔吐など)
・重篤な感染症、手術前後、外傷
・スルホンアミド系薬剤に対する過敏症の既往歴
・妊婦または妊娠の可能性がある
慎重投与
以下に該当する場合は、慎重に投与する必要があります。
・肝機能または腎機能障害がある場合
・脳下垂体機能不全または副腎機能不全のある方
・高齢者
・栄養不良状態、飢餓状態、食事の不規則または不足、衰弱状態
・激しい筋肉運動をする場合
・過度のアルコール摂取がある場合
相互作用
併用により血糖降下作用が増強または減弱する恐れがあります。
併用薬の種類により、低血糖または高血糖を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
増強する可能性のある薬剤(低血糖のリスク)
・インスリン製剤
・クロフィブラート
・ビグアナイド系薬剤
・アスピリン(サリチル酸剤)
・β遮断薬(プロプラノロールなど)
・α-グルコシダーゼ阻害剤(アカルボース、ボグリボース)
・ピラゾロン系消炎鎮痛薬(フェニルブタゾンなど)
・プロベネシド
・クマリン系抗凝固薬
・モノアミン酸化酵素阻害剤(MAOI)
・サルファ剤
・クロラムフェニコール
・テトラサイクリン系抗生物質
・クロフィブラート
減弱する可能性のある薬剤(高血糖のリスク)
・副腎皮質ホルモン
・アドレナリン
・甲状腺ホルモン
・フェノチアジン系薬剤(クロルプロマジンなど)
・卵胞ホルモン
・利尿剤
・ピラジナミド
・イソニアジド
・ニコチン酸
・アドレナリン
妊婦・産婦・授乳婦等への投与
妊婦または妊娠の可能性がある場合は使用しないでください。
授乳中の使用は避けることが望ましく、やむを得ず使用する場合は授乳を中止してください。
保存等
直射日光や湿気を避け、室温で保存してください。小児の手の届かない場所に保管してください。